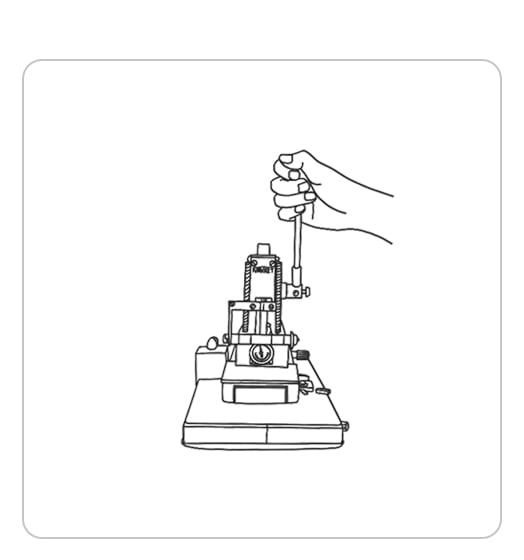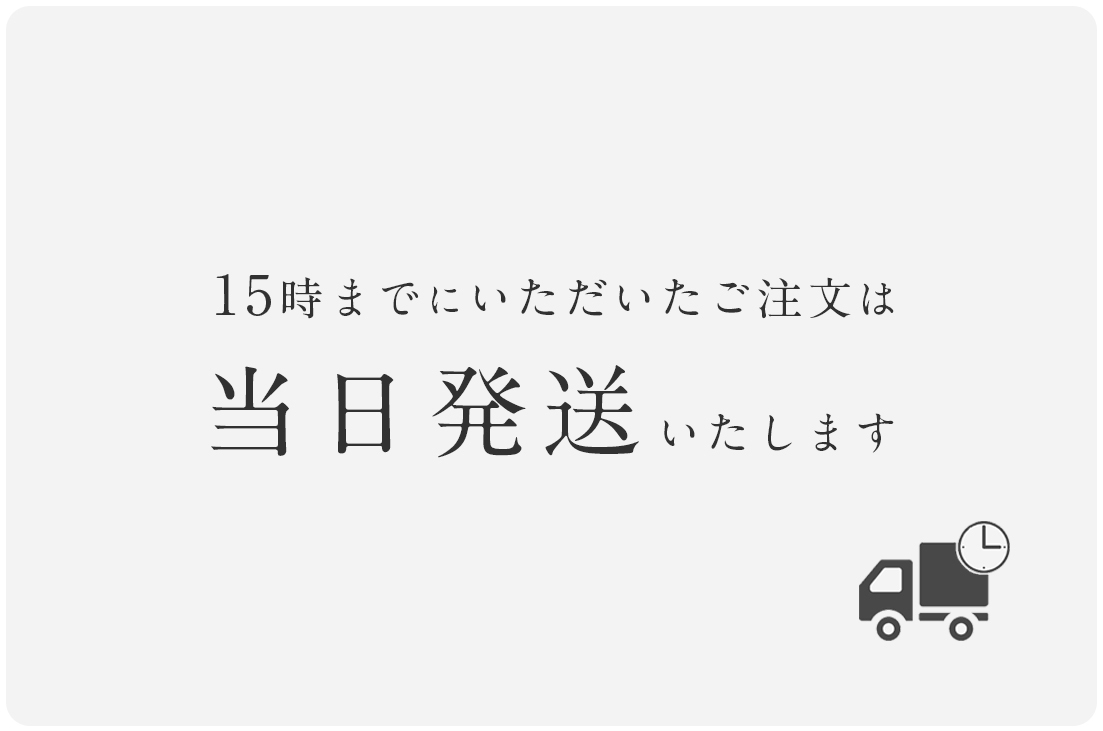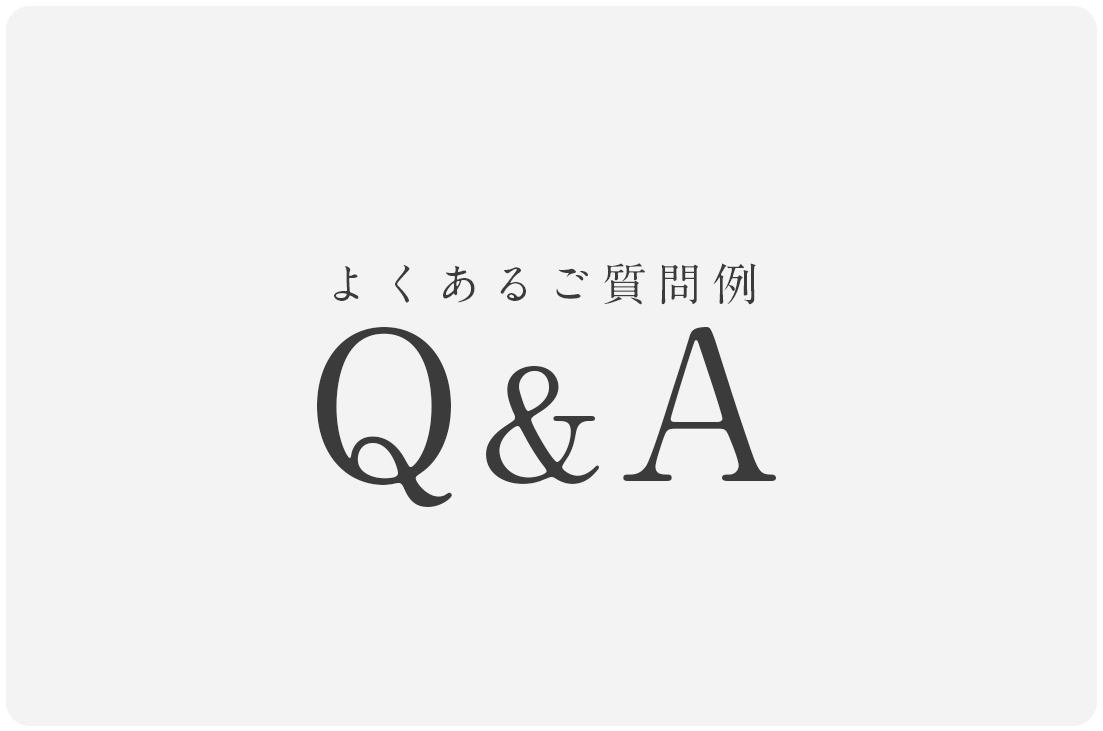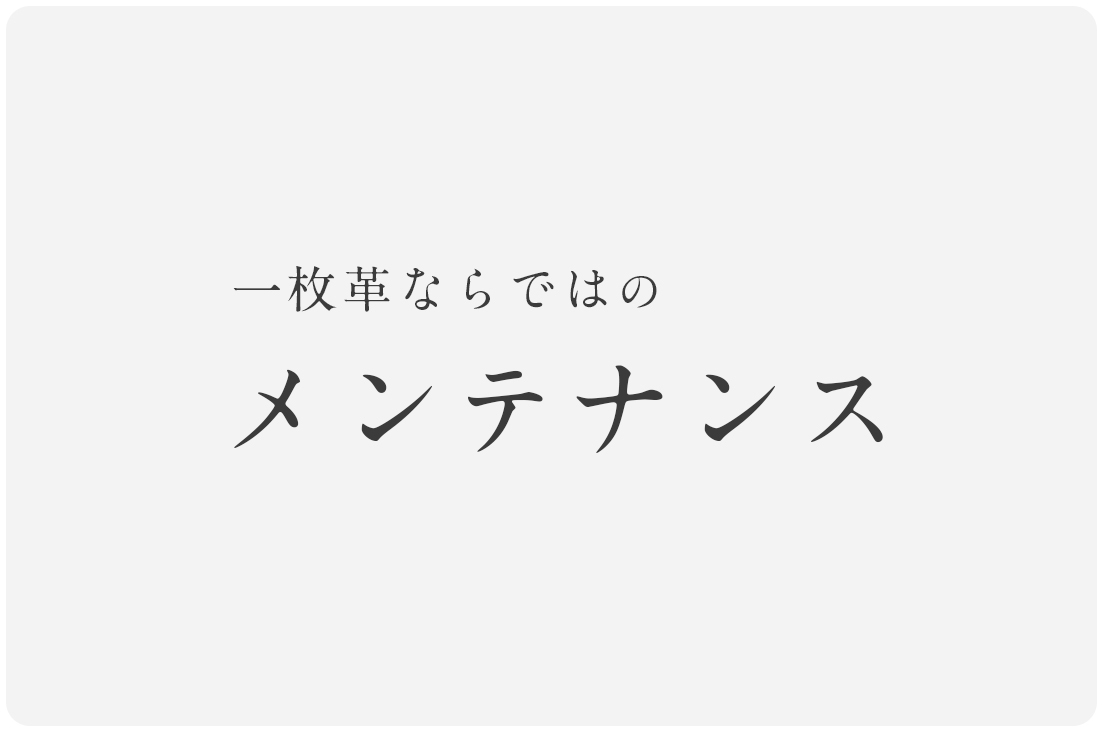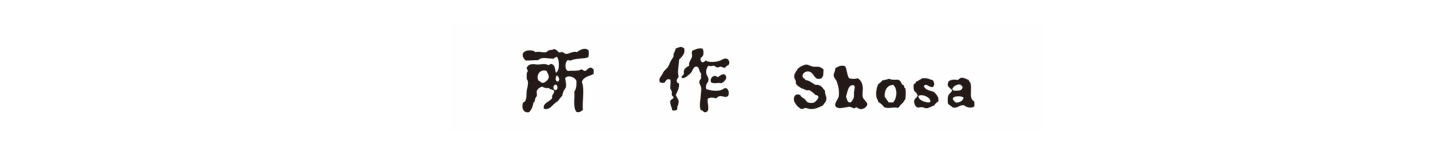Contents
2022/10/22 00:00
サムライ以来の伝統を現代ファッションに、と名高い「姫路黒桟革(ひめじくろざんかく)」。 決してキラキラと反射する訳ではなくて「暗く輝く」ような日本らしい慎ましく厳かな光。今ブログでは、その特徴と魅力について書いています。 革の宝石と言えば「コードヴァン」、黒桟革は小さなダイヤの粒を散りばめたような美しさを持つことから『革の黒ダイヤ』と呼ばれます。 (簡単に説明・・・表面の凸凹を利用し、漆を塗ることで輝きを出しています) 日本古来の伝統技法である『なめしの技術』と『漆塗りの技術』を融合させたのが、1923年創業、姫路タンナー“坂本商店”の誇る、姫路黒桟革(くろざんかく)。まず漆についてのご紹介です。 革は、国産の黒毛和牛を用いています(姫路白革なめし)。 ※※※※ 補足ですが、通常革製品に用いられる革は食肉加工過程の副産物です。余すことなく、動物の皮を利用しています。 漆と革との相性を鑑み、下地革をつくるところからはじめ 鞣しと漆塗り、それぞれの特性と物性を知り尽くしてつくられる革です。 坂本商店さんは、 黒桟革の歴史的背景と日本独自、独特な素材イメージから とコンセプトし、姫路から世界へ発信されています。 2014年 香港APLFアワードMM&T展(素材展)にて日本人初のベストニューレザー部門グランプリを受賞 2016年 パリの国際的なファッション見本市「プルミエール・ヴィジョン」が主催するPVアワードで日本企業として初めてレザー部門で「ハンドル賞」を受賞 以降、海外ファッションウィークでの黒桟革を用いたブランド展示など 日本よりも先に、海外で評価を得ているような印象すら受けます。 漆器という言葉が代表的に、漆と言えば「お椀」を想像される方も多いと思います。 生活の中であったり、伝統的な行事で目にしたり、 美しい、綺麗など感覚的な視点で語られることが多く思いますが そもそも 漆とは、一般的に漆の木の樹液を指す天然の塗料のことであって、木材や陶器という物に漆を塗ったものが漆器となる訳です。 その実、漆の木は中国からきている外来種の木、と説がありますが 最古の漆を塗ったものとしては縄文時代のものが見つかっており、9000年前から日本に存在するのだとか。 日本大陸の環境下では在来種と比べて弱い存在である外来種は、保護、管理しなければ生息することはできず それ以前よりも日本人は管理、必要としてきた、ことになります。 芸術性の高いもの、というよりも機能性から 塗料や接着剤など様々な用途で使われて、その丈夫さから自然界最強の天然塗料と言われています。 縄文時代のものでも、矢の先を漆で接着した実用的なものや漆で破損箇所を接着した器が見つかっているそうな。 身近かどうか定かではありませんが、「漆黒(しっこく)」という言葉は、漆を塗った黒の深さや艶やかさが語源だそうです。 そして、ある時代には 世界に漆=Japanと言わしめた芸術性はあったが、今では原材料のほとんどが海外にたよっています。 世の流れとは いつの間にか、あっという間に変わっていくものだ、と改めて、思います。 *こちらは藍染工程。手間と時間を要するのだが、まだ下地。ここから漆塗りへ 姫路タンナー“坂本商店” 現在では3代目 一家相伝の漆の技術を先代より受け継ぎ、世界へ発信した御方。 誰もが知る世界の某ブランドから声がかかり 日本の革ではなく、フランスの革で漆を〜という商談にもバシッとNoと言ったそうで。 このエピソードだけでも、ものづくりへの徹底した姿勢とこだわりを感じますが、お話を伺っていると 楽しさ、ロマンを感じることができて、たびたびサスティナブル(持続可能な)、エコなどのワードも出てきました。 言葉では簡単に言えますが、簡単ではないですよね。 常に「現代」での試行錯誤の創作を続けられている姿勢が素晴らしく、背筋の伸びる思いをしました。 >> ここ姫路市には、タンナーが集まっている一画、地区が存在します。 川沿いにあって、タイコといって革を回す木製の機械をよく見かけます。(稼働している、していないはおいといて) 姫路は、昔ながらの日本最古の革生産地として存在しているが 少々過去、のような名残りに近いところもあります。(あくまで個人談ですが) いいものをつくる、と言えば単なる素材の話になるのかもしれないけれど でも、 手元にあるものが 何百年、何千年、何万年の歴史を感じられて、起源を識るような奥行きがある。 それがまた、伝統を守ると言ってはおこがましい話なのですが 自国の伝統を受け継ぐ、ような感覚を持てるのは、大変にじわじわくる素敵なことだと思います。 ユーザーのもとに届いて、ちゃんと使われる。 これってすごくシンプルなことなんですが、単なるいいもの・いい素材では叶わないことだと思いませんか? そんな坂本商店さんとの出会いにて ※昼の太陽光と夜の照明下では輝きが異なります 不意に眺めるとキラキラしていて、『革の黒ダイヤ』って表現がわかる気がします。 About 所作より抜粋 _____布を広げ、贈りものを見る喜びを演出するための袱紗(ふくさ)がモチーフ。六百年以上の歴史がある様式、礼儀作法「折形」。 “お金を包む”動作自体を所作としてデザイン
凛とした立ち居振る舞い。
そんな美しい自然な動作に「美」を見出す日本のココロ。_______
いつの時代でも 身分を問わず誰もが憧れ、つくる人みる人の美意識を駆り立て 世代を超えて使い込まれた漆。 漆と革、黒桟革と所作、日本らしさ ぜひご堪能ください。 坂本商店特注 補色ケアクリーム(各色) 所作黒桟革をお使いの上、万が一のお困りの際はご相談ください。 長年の使用にも安心ですね。 *実際に黒桟革が用いられた甲冑。随所に煌びやかさを感じます それでは、また。 nakabayashi 20/02/27 ブログより

・「漆(うるし)」と「革」
・ 姫路から世界へ 坂本商店の伝統技法
・ 僕たちの日常に密着してきた漆
・ 現代のものづくり
・ 黒桟革と所作
















藍染のご紹介へ